臨床工学科
臨床工学技士は通称 “ME” と呼ばれ、医療機器の保守点検・管理・操作などを担う専門医療職です。病院内で、医師・看護師や各種の医療技術者とチームを組んで生命維持装置の操作などを担当しています。 また、医療機器がいつでも安心して使用できるように保守・点検を行い、安全性確保と有効性維持に日々努めています。
スタッフ紹介
当科は、医師1名、臨床工学技士12名、助手1名で構成されています
| 科長 井上 光《日本麻酔科学会専門医、麻酔科標榜医》 技師長 小林 勝(医療機器安全管理責任者、透析技術認定士、 医療機器情報コミュニケータ) 主幹 長尾 文彦 副技師長 中里 正樹(消化器内視鏡技師) 主任 今野 政憲(透析技術認定士)、日下 一 伊藤 翔太(消化器内視鏡技師)、佐藤 初衣、藤井 一棋 福井 隆一、秋本 真聖、品田 一顕、長谷川 豊(会計年度任用職員) |
臨床工学技士の業務

透析業務

透析センターでの業務は、透析液作成時に必要な水道水の水質や透析液の管理、透析装置の点検と操作です。また、患者様への穿刺(針を刺すこと)も行います。
透析中は、時間ごとに患者様の状態をチエックし、透析装置の点検もしながら安全に透析が行われているかを確認しています。
透析装置を定期的にオーバーホールし、故障やトラブルなどを未然に防ぐのも、臨床工学技士の仕事です。

ICU(集中治療室)業務

ICU内では、呼吸器の毎日の動作点検や回路の交換などを行い、夜間・緊急時にすぐに使用できるようにあらかじめ点検・準備をしています。
各種急性血液浄化として、CHDF(持続血液濾過透析)・PE(血漿交換)・エンドトキシン吸着・DHP(血液吸着法)・顆粒球吸着などを行っています。
写真は、血漿交換をしながら、CHDFを同時に施行しているところです。

心臓カテーテル検査業務

検査前の機器の立上げ準備、患者さんへの心電図電極の装着や検査中の心電図変化の記録などを行います。
また、定期検査の他に夜間・休日における緊急時の心筋梗塞にも対応しています。
・体外式ペースメーカー操作
・大動脈内バルーンパンピング(IABP)機器の操作
・除細動装置の設定など


手術室業務

手術室には、麻酔器をはじめ多種多様のME機器があります。それらの機器を手術前に安全に使用できるように点検します。
手術中にも、それらのME機器の操作やトラブル発生時の対応をしています。

ペースメーカー外来業務

平成21年3月から、ペースメーカー外来での業務を始めました。
ペースメーカーの植込み手術に立会い、植込み直後の設定チェックやペースメーカー外来にて植込み後6ヵ月毎にペースメーカーが正常に作動しているか、バッテリーの残量はどれくらいかなどをチェックします。
写真ではプログラマと呼ばれる機械を使い、ペースメーカーのチェックを行っているところです。
また、ペースメーカー植込み患者様のデータ等も管理していて、患者様に植込み後6ヵ月毎のペースメーカー外来診察日の案内を郵送しています。

内視鏡検査業務

平成23年4月から、消化器内視鏡技師の資格を取得した臨床工学士2名がが中心となって内視鏡検査業務を行っています。
胃カメラ・大腸カメラの検査介助や胃・大腸ポリープ切除時および膵・胆管の処置時の補助をしています。その他、当院では小腸ダブルバルーン内視鏡、小腸カプセル内視鏡検査も行っているため、検査の補助や予定管理なども行います。また、検査に使用する内視鏡カメラの洗浄・消毒管理や機器の保守メンテナンスを行い、安心・安全に検査が受けられるようにしています。

ME機器管理業務

院内で使用される共用機器を安全に使用できるようME機材管理室でME機器管理ソフトを使い、効率よく貸し出し・返却が出来るようにしています。
返却時は終業点検により、動作の確認を行い正常であれば、貸出可能としています。
故障している機器は院内で修理し、修理不能な機器はメーカーに預け、スムーズに復帰できるように依頼します。
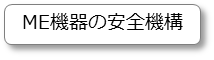

最近の医療機器(ME機器)には、さまざまな新しい安全装置が付いています。
例えば、写真はT社のME機器であるシリンジポンプです。シリンジポンプとは薬液を注射器(医療現場ではシリンジと言います。)にて持続的に微量注入する機器のことです。
この機器を例にしてみると、まず外観の違いとして1時間当たりに何ml注入するのかと言う、いわゆる流量を表示する部分が以前と比べ整数桁と小数点・少数桁を色分けし、サイズを変えることにより、流量設定の間違いを予防するようになっています。
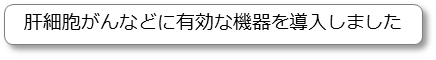
肝細胞がんの治療として、最近体への負担が少ない経皮的ラジオ波焼灼l療法(RFA)が数多く行われるようになってきました。2004年4月から保険適応になったこの治療は腫瘍の中に直径1.5mmの電極針を挿入し、電極周囲を450kHzの高周波(ラジオ波)によりがんを凝固壊死させる治療法です。

原発性肝がん(肝細胞がん)、転移性肝がんのいずれにも効果があり、一般的には大きさ3cm、個数3個までならRFAで十分に治療できると考えられています。当院にRFA機器が導入されたことにより、この治療が可能となりました。

RFAが適当とされる条件は…
●切除不能であるか、外科的切除を希望しない場合
●病変の最大径が3cm以内で、かつ3個以下の場合
●コントロール不能の腹水がない場合
●ペースメーカーを植込みしていない場合などがあります。
詳しくは当院外科外来までお問い合わせください。








